スタートアップ支援での知財トラブルと弁理士の対応術
 岩崎 禎
国内製薬企業勤務、NATAコーポレーション 知的財産部長、いわさき総合知的財産事務所 代表弁理士 他多数
岩崎 禎
国内製薬企業勤務、NATAコーポレーション 知的財産部長、いわさき総合知的財産事務所 代表弁理士 他多数
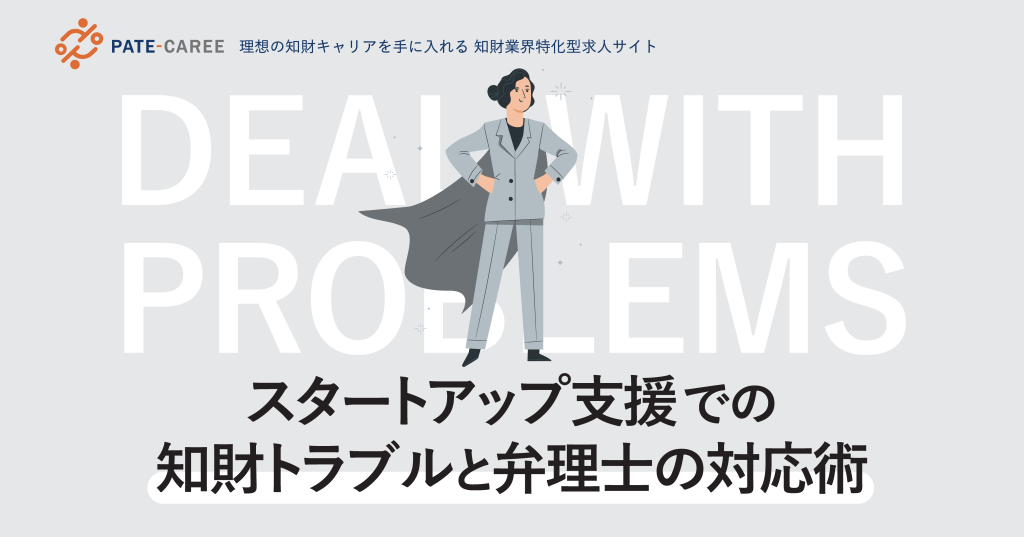
早期対応で致命傷を防ぐ、知財の専門家が果たす役割
今回は、私がこれまでの社会人経験の中で、また、NATAコーポレーションで様々なスタートアップの方と接する中で、経験してきたことにも基づきながら、スタートアップが陥りがちな知財トラブルと弁理士が支援できる対応術について書いてみたいと思います。
スタートアップが事業を軌道に乗せる過程で、意外と見落とされがちなのが知的財産(知財)に関するリスクです。限られた資源のなかでスピード重視の事業展開を進める一方で、後手に回った知財管理が原因で、後になって大きなトラブルに発展するケースは少なくありません。ビジネスの世界は知らなかったではすまされないことにあふれています。
こうした知的財産トラブルを未然に防ぎ、解決に導く専門家こそが「弁理士」です。本記事では、スタートアップ支援の現場で実際に起こり得る知財トラブルの具体例と、それに対して弁理士がどのように対応し、どのような価値を提供できるのかを、解説します。
トラブル事例①:共同研究・共同開発で生じる「発明の帰属」問題
近年、スタートアップが大企業や大学などと連携して研究開発を行うケースは増加傾向にあります。しかし、ここでよく問題になるのが「誰の発明か」(誰に帰属するか)」という論点です。
特許法では、発明を行った者が発明者とされます。また、その発明が職務発明に該当する場合に、その発明者が所属する法人に特許を受ける権利を原始帰属(発明発生のタイミングから帰属すること)や承継することを定めることが可能です。
ところが、スタートアップが絡む取引においては、契約書でその点が明確にされていなかったり、開発プロセスの研究データの記録や役割分担が曖昧だったりすると、後になって「この技術はうちのものだ」と相手方から主張されるトラブルが発生します。
弁理士がこのような場面で果たす役割は多岐にわたります。
たとえば、開発初期の段階からかかわることができるケースでは、発明創出のデータ管理体制を整えたり、職務発明規定を整備したりすることが可能です。
特に、データ管理体制において、発明者たる技術者が理解できるレベルでよい場合もありますが、将来的に特許出願等を行い権利化を狙っていく場合には、発明ノートの記録方法などから権利化を見据えた体制づくりにおいても弁理士の知見が活きてきます。
また、協業先との連携が始まる段階からかかわることができるケースでは、共同研究契約や共同開発契約に知財の帰属に関する条項を明記するようアドバイスしたりすることが可能です。スタートアップにおいては知財と法務をおひとりが兼ねていらっしゃる場合も少なくありませんが、その場合であっても多忙な担当者さんが見落としているかもしれないポイントを弁理士のアドバイスによって気づいてもらうことも可能かもしれませんね。
トラブル事例②:競合からの「特許侵害警告」
スタートアップが新しい製品やサービスを展開し始めた途端、ある日突然「貴社の製品●●は当社の特許権××を侵害している」といった警告書が届くことがあります。 こうした特許侵害の警告書は、競争戦略としてあえて強めの表現に出されることもあり、スタートアップにとっては大きなプレッシャーです。
このようなとき、弁理士はまず警告書を送付してきた企業の当該特許の権利範囲や権利の有効性、製品との関係性などを精査・鑑定し、スタートアップにとって最善の対応策を提案します。
非侵害であることが明確であれば、その旨を書面で相手方に送付して回答することもあるでしょう。しかし、警告書を送付してくる段階では相手方も闇雲に送付しているということはあまりなく、ある程度の自身や確度をもって送付してきています。
下手な対応をとることで、場合によっては「特許権侵害訴訟」に発展することもありえます。そんなときにスタートアップの側に立つ弁理士としては、「特許無効審判」を請求して無効な特許による侵害訴訟は権利の濫用だと表明するなど、積極的な対応に出ることも可能です。
本来であれば、このような事態に発展する前に、事前に「他社特許の調査」(FTO調査またはクリアランス調査ともいいます)を行っておくことで、こうしたリスクを回避できることもあるでしょう。
スピードが勝負のスタートアップにとっても、製品ローンチ後に市場からの撤退や損害賠償の支払い等の事態になり「知的財産に関する意識が低い」と評価されてしまう前に、弁理士と連携し、クリアランス調査を徹底することが経営者にとっては鍵となりますし、弁理士もその点をアピールすることが重要です。
トラブル事例③:商標の「先取り登録」によるブランディング妨害
スタートアップが、これから販売しようとする商品やサービス名をSNSやWebで告知した後に、第三者がその名称を先に商標登録してしまう、いわゆる「商標のハイジャック(商標ブロッキング)」もよくあるトラブルです。
このような場合、本来使用を希望しているブランド名を使えなくなったり、法的措置に時間とコストがかかってしまったりと、せっかくのブランディング戦略が台無しになることもあります。
このような場合においても、弁理士の支援があれば、このリスクは大幅に軽減できます。事業開始前に商標登録を済ませるのはもちろん、複数のバリエーションを抑えておくことで、商標トラブルを防ぐことが可能です。
また、悪意のある商標出願であると判断できる場合には、登録異議申立や登録無効審判請求といった法的手段で対抗する道もあります。
さらに、商標に関してはすでに第三者が商標権として取得している名称等をスタートアップが使ってしまうリスクもあります。その場合、当該第三者から商標権侵害を警告される事態となる場合もありますので、特許の場合と同様に、事前に第三者の商標権を侵害していないかどうかの調査を徹底しておくことが望ましいでしょう。
なお、過去にはこのようなトラブルに関連して、多数の未使用の商標出願を繰り返して、権利譲渡やライセンスの相談を持ち掛けてきた企業に対して権利の売買をすることを行っていた企業も存在しましたが、現在はその重大さから商標法が改正されてこのような事象は起こりづらくなっています。
トラブル事例④:元従業員による「ノウハウ流出」
スタートアップは基本的に少数精鋭です。また、所属する方々もそれぞれやりたいことが違う場合もあります。創業期のビジネスに興味がある方もいれば、かかわった製品のローンチまで見守ってくれる方もいるでしょう。
スタートアップが成長するにつれて、創業期から支えてくれた優秀な人材が転職・独立していくことも増えてきます。 その際に問題になるのが、在職中に知り得たノウハウや営業秘密を持ち出してしまうケースです。
たとえば、顧客リスト、顧客の名刺情報、契約の情報、製品に関するアルゴリズム、製造ノウハウなどが無断で使用されたり、競合会社で類似製品が開発されたりといった事態が発生する可能性があります。
このような事態に備え、弁理士は秘密保持誓約書を従業員との間で交わしておくことや就業規則への秘密保持条項の組込み、営業秘密としての管理体制の整備などを提案・支援することができます。
また、特許出願や意匠出願により、技術やデザインを権利化しておくことも技術やアイデアの抑止力になります。
弁理士がスタートアップにもたらす3つの価値
以上のようなトラブル事例を通じて見えてくるのは、弁理士の介入が単なる「出願代行」にとどまらないということです。スタートアップに対して、次のような価値を提供しています。
①予防的なリスクマネジメントの支援
発明の管理、商標の早期取得、契約条項への助言などにより、将来を見据えて、係争・紛争を未然に防止できるリスクマネジメントの価値が提供できます。
②スピード感のある事業展開の伴走
特許戦略・商標戦略を事業計画に組み込み、資金調達や出口戦略との整合性を図ることで、成長を後押しします。タイミングに応じた出願・権利化戦略をとることで、ビジネス基盤を盤石にし、事業展開を権利の側面から伴走支援できる価値が提供できます。
③トラブル発生時の専門的な対応力
権利侵害の警告対応や無効審判請求、係争対応において、弁理士が専門家として矢面に立ち、事業を守る価値が提供できます。特に、係争対応については特定侵害訴訟代理付記資格を有する弁理士であるほうがより好ましいケースも生じてくるでしょう。
まとめ:スタートアップも知財は“後回し”にしない
スタートアップの多くは、「知財は後でいい」「特許はお金がかかる」といった理由で対応を先送りにしがちです。残念ながら弁理士が支援を行う際もよく聞く言葉です。
通常、スタートアップは資金難であることが多いため、経営者の意見もビジネスの視点に立つと理解できなくはないのですが、知財をめぐるトラブルは、ある日突然発生し、事業の成長を一瞬で止めてしまうほどのインパクトを持ちます。どれだけ素晴らしいビジョンをお持ちのスタートアップ企業であっても、知財トラブルは会社倒産にすらつながる可能性もある大きなリスクなのです。むしろ、初期段階だからこそ正しい知財戦略が必要です。
弁理士は、技術・ビジネス・法務の橋渡し役として、スタートアップの知財に関するあらゆる場面に寄り添い、事業成長の支えとなる存在です。
もし少しでも知財に不安があるというスタートアップの方が読んでいらっしゃる場合は、まずは気軽に弁理士に相談してみることをおすすめします。
そして、スタートアップ支援を行いたいと考えている弁理士の方が読んでいらっしゃる場合は、これまで紹介してきたようなトラブルに対する事前・事後の対応策の十分な知識・経験を今のうちから積んでおくことを強くお勧めいたします。
 岩崎 禎
国内製薬企業勤務、NATAコーポレーション 知的財産部長、いわさき総合知的財産事務所 代表弁理士 他多数
製薬企業での研究者時代に知財に出会い、その後どっぷり知財の道へ進む。医薬・医療機器・医療用アプリ分野を中心に、企業内弁理士の観点で特許・商標と幅広く従事している。また、長年にわたり知財教育等の教育活動も続けている。(株)NATAコーポレーションの知的財産部長として、フレンドリーCRO®システムを活用した創薬ベンチャーの業務支援やコンサルティングに携わりつつ、いわさき総合知的財産事務所の代表弁理士、東和国際特許事務所の弁理士としても幅広くクライアント様への知財サポートを提供している。
岩崎 禎
国内製薬企業勤務、NATAコーポレーション 知的財産部長、いわさき総合知的財産事務所 代表弁理士 他多数
製薬企業での研究者時代に知財に出会い、その後どっぷり知財の道へ進む。医薬・医療機器・医療用アプリ分野を中心に、企業内弁理士の観点で特許・商標と幅広く従事している。また、長年にわたり知財教育等の教育活動も続けている。(株)NATAコーポレーションの知的財産部長として、フレンドリーCRO®システムを活用した創薬ベンチャーの業務支援やコンサルティングに携わりつつ、いわさき総合知的財産事務所の代表弁理士、東和国際特許事務所の弁理士としても幅広くクライアント様への知財サポートを提供している。


